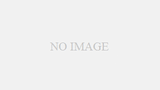この記事は約 13 分で読めます。
生命保険の必要保障額が足りているかってとっても気になりますよね。
特に死亡保障の場合、自分にもしものことがあった後残された家族が困ることのないようにしたいと皆さん思っているでしょう。
多ければ多いにしたことはないかもしれませんが、保障はかけすぎると家計に負担がかかってしまいます。まずは必要な保障額をしっかりカバーできる保険に加入しましょう。
死亡保障の必要保障額計算方法
もし自分が無くなってしまった場合、どんな費用が必要だと思いますか?
すぐに思いつくのは残された家族の生活費や葬儀代でしょうか。
子供がいる場合は学費も必要でしょうし、住居のことも考えないといけないですね。
ですが、支出ばかりではありません。
子供や妻が残された場合は社会保障を受けることができるので必要保障額は必要保障額積み上げ方式で計算します。
遺族に必要な生活費等の総額-収入=必要保障額
独身の必要保障額
独身の場合、お金を残してあげる人がいないため、自分のお葬式代や遺品整理などにかかる費用を準備しておけば十分ですね。
お葬式費用は2017年の日本消費者協会の調査では約196万円でした。その他の費用も含め余裕をもって考えると300万円ぐらいが必要保障額になります。
ただしローンなどの負債がある場合はその分も必要保障額が上乗せされます。
自分に万が一のことがあった時、両親や兄弟に借金を残しておくわけにはいかないからですね。
夫婦だけで子供がいない場合
自分に万が一のことがあった場合、配偶者には一生困らないだけのお金を残したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
残された配偶者は悲しみに暮れてしまうかもしれませんが、やがては新しい生活を始めることになるでしょう。その期間の費用を準備しておきましょう。
若い夫婦の場合はいずれ仕事も始めたりするでしょうから、それまでの生活費として一般的には1,000万円ぐらいを必要保障額として考える方が多いようです。
子供が巣立って扶養する必要のない夫婦の場合もあるでしょう。
年齢を重ねていることもあり専業主婦が残された場合は就職もむずかしいかもしれませんね。
このような場合は働かずに暮らせるだけの保障が必要保障額になります。
妻が50歳の場合、厚生労働省の「簡易生命表」を見てみると平均余命は38年。
夫婦暮らしの生活費が半分になるとして計算してみましょう。
仮に月の生活費を13万円で計算してみましょう。
13万円×12ケ月×38年=5,928万円
ちょっとびっくりな金額になったかもしれませんが、預金や遺族年金、自分がもらう年金などを差し引きすると実際には2,000万円ほどの保障でまかなえるでしょう。
亡くなった配偶者が会社員や公務員などの場合、遺族厚生年金が一生涯もらえることは大きな安心にもなりますね。
扶養している子供がいる場合
まだ親の扶養家族である子供がいる場合は計算が複雑になります。
子供たち自身は保障が足りなかったとしても足りない分を働いて補うことはできないのですよね。そのため子供に必要と思われる分はしっかり準備しておくことが大切です。
必要保障額を求める一般的な計算方法「必要保障額積み上げ方式」で計算してみましょう。
遺族に必要な生活費等の総額-収入=必要保障額
まずは遺族に必要な費用から見ていきましょう。
・生活費
・教育資金
・結婚費用
・住居費用
・葬儀費用
・その他予備費
それぞれの計算方法や概算額を見てみましょう。
1)生活費
末子が独立するまでの費用と末子が独立後、配偶者だけになったときの生活費に分けて考えましょう。
末子独立までの遺族の生活費
末子が独立するまでの期間は、現在の生活費の約70%を目安として計算します。
末子独立後の配偶者の生活費
配偶者が一人で平均余命まで生活する期間は、現在の生活費の約50%を目安とし手計算します。
2)教育資金
<文部科学省「子供の学習費調査」/平成28年度>
| 公立 | 私立 | 必要期間 | |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 23万円 | 48万円 | 2~3年 |
| 小学校 | 32万円 | 153万円 | 6年 |
| 中学校 | 48万円 | 133万円 | 3年 |
| 高等学校 | 40万円 | 99万円 | 3年 |
| 大学 | 4年間費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 約530万円 | 下宿の場合 約300万円プラス |
| 私立文系 | 約690万円 | |
| 私立理系 | 約820万円 |
3)結婚費用
結婚費用の援助をする予定があれば計算に入れておきましょう。ゼクシィが実施した2016年の調査では約77%の人が親や親族から援助を受けていてその額は平均189万円でした。
これまで相談を受けた中では、片親になったとしても相手の家のこともあるので準備しておきたいという方が多かったですね。
4)住居費用
持ち家の場合はローンを組む際に万が一のための保障に加入しているため、ローンの返済が不要になりますが、リフォーム費用を考えておく必要があります。
賃貸の場合はその費用を計算しておきましょう。
賃貸の場合:賃貸月額×12か月×妻の平均余命
5)葬儀費用
葬儀費用については300万円程度準備しておきましょう。
6)その他予備費
10年に一度は車を買い替えたいとか、旅行したいとか予定があるならばその費用を見積もっておきます。
ではここでちょっと計算してみましょう。
家族構成・・・妻38歳、長女10歳、長男8歳
持ち家、住宅ローン残高あり(団体信用生命保険加入)
現在の生活費月額26万円
1)生活費
末子独立まで:26万円×0.7×12か月×15年=3,276万円
末子独立後:26万円×0.5×12か月×35年=5,460万円
2)教育費
どちらの子供も高校まで公立・私大文系で自宅通学
長女:1,055万円
長男:1,108万円
3)結婚資金
長女。・長男とも100万円援助予定
200万円
4)住居費用
住宅ローン加入のため保険金でローン完済
リフォーム費用として準備
500万円
5)葬儀費用
300万円
6)その他費用
300万円
積み重ねてみると結構な金額になりますね。そしてこれだけの金額を用意しておくなんて無理!と思うかもしれませんね。
ですが、ご安心ください。
必要保障額積み上げ方式で計算するときに残された遺族に必要な生活費等の総額から遺族年金や預貯金などの収入を差し引くとあったように、収入の大黒柱が亡くなったからと言って収入が0円になるわけではありません。
大黒柱が亡くなった後にどのような収入が見込めるのか確認してみましょう。
遺族が受け取る収入
1)社会保障
年金制度の加入していることによって遺族基礎年金や中高齢寡婦加算、遺族厚生年金といった社会保障を受けることができます。
子供が18歳になるまでの遺族基礎年金や妻が受け取る老齢基礎年金、厚生年に加入していれば遺族厚生年金を一生涯うけとることができます。
2)企業保障
会社員ならば退職金や慰霊金などを受け取ることができるでしょう。
3)預貯金
収入とはちょっと違いますが、これも将来使える費用として計算にいれておきましょう。
4)その他収入見込み
今は働いていないとしても、大黒柱が亡くなった後、残された家族も全く働かないということはないでしょう。勤めに出たとしての収入を見込みましょう。
では、収入見込みとしてどれぐらいの金額になるのか確認してみましょう。
Aさんが厚生年金に加入しており、平均標準報酬額を39万円として計算してみましょう。
1)社会保障
長女が10歳~18歳まで:1,538万円
※遺族基礎年金、遺族厚生年金
長男が17~18歳まで:297万円
※遺族基礎年金、遺族厚生年金
妻49歳~64歳まで:1,705万円
※遺族厚生年金、中高齢寡婦加算
妻65歳~87歳まで:2,899万円
※老齢基礎年金+遺族厚生年金
会社員なのか自営業かで社会保障の額は変わります。自営業の場合は遺族厚生年金と中高齢寡婦加算がありません。
2)企業保障
退職金や弔慰金など:400万円
3)預貯金
今現在の資産額:600万円
4)その他収入見込み
妻40歳~60歳、パート年収100万円
100万円×20年=2,000万円
これで大黒柱が亡くなった後に必要な資金と収入が計算できました。
この結果から必要保障額を計算しましょう。
必要費用合計-収入見込み合計=必要保障額
12,249万円-9,439万円=2,810万円
必要費用合計が1億円を超えたときはどうしようかと思った方も社会保障が意外と充実していることに驚かれるのではないでしょうか。
例を見てみると、必要費用が1億2千万円を超えていても保険で準備する額は2,810万円です。
この計算はあくまでも現時点で亡くなった場合の計算額です。子供が大学を出てた後なら学費は必要なくなりますし、貯金が増えれば保険で準備する額も減るでしょう。
保険の見直しが何度か必要になるのはこういった家族の状況が変わっていくからなんです。
必要費用の合計は自分で出せても、自分だと社会保障でどれぐらいもらえるのかさっぱりわからないという場合は、保険会社のサイトで準備している簡易版の必要保障額計算やファイナンシャルプランナーまたは保険会社の担当に相談してみましょう。
保険の担当者に相談する場合でも必要保障額の出し方を自分が知っていれば提案される保険が本当に必要な額なのかということが判断できます。
実額の計算はできなくても考え方は覚えておいてくださいね。
※会社員:妻・子供二人の例
まとめ
必要保障額は収入の大黒柱が亡くなったあと必要になる生活費などの必要費用合計から社会保障で補填される額や現在の預貯金額を差し引いて計算します。
計算例では40歳の会社員で子供二人の場合、2,810万円が必要保障額となりました。
ただしこれは、現時点での必要保障額になります。
家族構成が変わったり仕事が変わったり、賃貸から持ち家になったなど環境にもよって必要保障額は変わります。
保険の見直しというと保険料が払えなくなったからという理由が多いのですが、保険料が払えていたとしても家族を取り巻く状況によって必要保障額が変わっているので、何年かに一度は見直しを考えましょう。
自分で必要保障額を計算できないとしても、提案される保険が自分にとって過不足ない額なのか判断するためにどういった費用を計算しておけばいいのかといったことは覚えておいてくださいね。