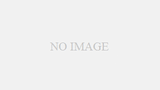この記事は約 9 分で読めます。
私たちは普段保険証を提示することによって何気なく病院へ行っていますが、そもそもなぜこんなに安く治療ができるのと考えたことはありますか?
なんとなく「負担が3割だから」と漠然と知っているものの、医療費の負担のことや高額になった場合の制度についてはわからないこともあるのではないでしょうか。せっかく加入している健康保険のことですから、くわし
く知っておきましょう。
医療費の一部負担割合とは
ケガや病気で病院に行くことになったとき、必ず持っていくものが健康保険証ですね。健康保険証を持っていくことによって医療費は一部負担で済みます。
一般的には3割負担の人がほとんどですが、義務教育就学前の幼児については2割負担、70歳以上の高齢者については2割負担、75歳からは1割負担(ただし、高齢者については現役並みの所得があれば3割負担となります)と
年齢や生活状況によって細かく設定されています。
| 一般・低所得者 | 現役並み所得者 | |
|---|---|---|
| 75歳以上 | 1割負担 | 3割負担 |
| 70歳以上 | 2割負担 | |
| 70歳未満 | 3割負担 | |
| 6歳未満 | 2割負担 | |
今では誰もが保険に入っており、健康保険証を当たり前のように持っていますが、実は1955年(昭和30年)くらいまでは無保険の人も多くいたんですよね。
その数は国民の約34%、約3000万人にのぼり貧困層の医療の格差が非常に問題となっていたのです。
そのため、1958年(昭和33年)に国民健康保険法が制定され、1961年(昭和36年)に全ての国民が何らかの保険に入る国民皆保険体制が達成されたんです。
たった3年で達成するんなんてすごいですよね。
早くに国民皆保険体制が達成されたのは、制定前に約66%の人が何らかの医療保険に加入していたことも理由の一つですが、大きな原動力は従業員5人未満の企業の従業員も国民健康保険への加入者としたことです。
国民皆保険となったことで国民病と言われ、死亡原因の第1位だった結核の制圧にも成功しています。
高額療養費制度とは
病院などで治療を受けると、かかった医療費の1割から3割の負担をします。残りは加入している健康保険機関からの支払いとなるため、私たちは普段は負担が少なく治療ができています。
しかし、症状などによりいくら一部負担とはいえ医療費が高額になってしまうと同様に自己負担の医療費が増えてしまうので家庭によっては重荷となってしまいます。
健康保険には、医療費の自己負担が大きくなりすぎないようにストップをかける高額療養費制度が健康保険や国民健康、組合保険などに設けられています。
高額療養費制度は月に自己負担した医療費が一定の限度額を超えると、超えた分を返還してもらえる制度です。
医療費自己負担額の上限計算方法
医療費の自己負担上限は年齢や所得によって金額が変わります。
69歳以下の場合
| 収入 | 自己負担上限 |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ~年収約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
※1つの医療機関等での自己負担では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(21,000円以上)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
例えば、Aさんが入院して医療費が100万円かかったとしましょう。
医療費の自己負担額は3割負担の30万円となりますが、かなり高額ですよね。
こんなとき、年収が年収約370~770万円の人であれば自己負担の上限額は87,430円と決まっていますので、超えた分の212,570円については高額療養費制度を利用すれば戻ってきます。
自己負担上限:80,100+(1,000,000-267,000)×1%
戻ってくる額:300,000-87,430=212,570
年齢や所得に応じて金額が変わりますが、お金が戻ってくるのであれば積極的に利用したいですよね。
高額療養費申請方法
とっても助かる制度ですが、健康保険機関によっては高額療養費は申請しなければ戻ってきませんので注意する必要があります。
また請求の権利には時効があり診察を受けた翌月の初日から2年間になっています。2年以内で時効になっていない高額療養費があれば過去にさかのぼって支給請求が可能です。
それではどのように申請すればよいのでしょうか。先ほどのAさんの例をもとに順番に見ていきましょう。
申請方法は事前にする方法と、前もって申請する方法がありますが、まずは窓口で医療費を支払った後で高額療養費を請求する「償還払い方式」について解説しますね。
償還払い方式
1)病院で負担額(100万円の入院費で3割負担であれば30万円)を一旦支払います。
2)Aさんの収入であれば自己負担の上限は87,430円であるため、超えた分は請求できることを確認します。ちなみに1カ月の間に他の家族で超えた分があれば合算して申請できます。
3)保険証に記載されている健康保険機関に書類を提出します。
主に以下のものが必要です。
・高額療養費支給申請書
・領収書
・保険証
・印鑑
・振込口座情報
4)振り込みで返金がなされます。手続き期間は保険によって違いますが、例えば協会けんぽの場合は少なくても3ヵ月程度かかります。
国民健康保険は高額療養費に該当するような場合、一般的に保険者である区市町村から申請書が送られてきますが、少しでも早く支給してほしい場合は届くのを待つのではなく書類を請求して手続きを行いましょう。
事前申請方式
あとで高額療養費が戻ってくるとしても、一旦支払う窓口での医療費が負担になることもあるでしょう。そんな場合のために窓口での支払いを自己負担の上限に抑える方法もあります。
加入している健康保険機関に「限度額適用認定証」の交付を受けましょう。
限度額適用認定証を病院の窓口で提示すれば自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。
限度額適用認定証申請手順
1)限度額適用認定申請書健康保険機関へ提出
2)限度額適用認定証を交付(発行までの目安:1週間程度)
申請書には病名などは必要ありません。入院が決まった時などは申請をしておくと安心ですね。
ただし注意したいのは病院ごとに計算するため、Aさんが二つの病院にかかった場合、「限度額適用認定証」提示してもA病院で87,430円、B病院でも87,430円まで自己負担額が必要になります。
合算して自己負担限度額を超える場合は、やはり高額療養費支給申請になるってことですね。
まとめ
健康保険に支払いを毎月負担に感じていたかもしれませんね。
ですが健康保険に加入していることで病気になったときでも、会社員であれば自己負担3割で済むし、自己負担が高額になっても申請することで実際の医療費が100万円だったとしても普通の会社員ならば9万円程度のですむ
のですから、いざというときに助かりますよね。
ちなみに日本の公的医療制度は世界でもトップレベルの待遇のよさとなっています。アメリカは「医療費は自分でなんとかする」というスタンスのため、日本のような制度はありません。そのため、盲腸の手術に300万円以
上かかるといわれています。
そのため借金で自己破産する人よりも、医療費破産をする人がずっと多いのだとか。
そう考えると、月々の健康保険料も「まぁ…払うか…」という気持ちになるのではないでしょうか。医療費が高額になった場合は高額療養費支給申請することを忘れないでくださいね。