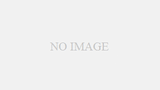この記事は約 9 分で読めます。
生命保険は残された家族のためだから、できるだけ保障を高額にしようと考える方もいらっしゃるかもしれませんね。実は生命保険は年齢や職業によってによって加入限度額が決まっているため希望するだけの保障金額に加入できないことがあります。
その理由は生命保険が相互扶助で成り立っているからなんです。
相互扶助とは多くの保険加入者が公平に保険料を負担しあい、もしものことが起きたときに給付を受ける仕組みです
やっぱり若い人よりも年齢を重ねた方のほうがもしものことが起こる確率は高いですよね。
保険会社は厚生労働省の患者調査の受療率を参考にした支払いのリスクに応じて引き受けをしているんです。
そのため、保険料の公平性を守るために職業や年齢で加入できる保障額に制限がかかってくるんです。
実際にどのような制限があるか見てみましょう。
年齢による加入限度額
生命保険なのでやっぱり年齢が加入限度に大きくかかわってきます。生命保険の加入の際告知でOKな保障額とお医者さんの診査が必要な保障額とでは差があります。
こちらでは告知書だけで加入できる保障額を保険会社ごとにまとめてみますね。
※年齢は保険会社の算定方法による
2018/2現在
ライフネット 100万円単位 定期保険80歳まで
かぞくへの保険
契約年齢
20~40:3000万円まで
41~45:2500万円まで
46~50:2000万円まで
51~55:1500万円まで
56~65:1000万円まで
アフラック 100万円単位 終身保険
アフラックの終身保険
45歳以下:2000万円まで
46~65:1200万円まで
66~70:500万円まで
アクサダイレクト 100万円単位 終身保険
20~49:4000万円まで
50~54:3000万円まで
55~59:2500万円まで
60~64:2000万円まで
65~69:1500万円まで
SBI生命 100万円単位 定期保険10年
クリック定期
20~39:3000万円まで
40~45:2500万円まで
46~49:2000万円まで
50~59:1500万円まで
60~65:1000万円まで
66~69:500万円まで
この契約限度額は各社ごとの限度です。
一つの保険会社で限度額まで加入しても、もっと必要であれば複数社で加入することができます。例えば各社合計で1億円の保障額で契約することも可能です。ただし合計1億円という保障が必要かは必要保障額をきちんと算出してくださいね。
ただし例外が1つだけあります。
被保険者が満15歳未満の場合は死亡に関する保険金は各社通算して1,000万円までしか加入できません。
※2008年7月3日 金融庁が規制義務化
死亡保険金は残された家族のための保障なので、両親が亡くなった時の保障が必要でも子供が亡くなった時の保障が必要とは考えにくいですよね。それと未成年の場合被保険者の同意が親権者でも可能なためモラルリスクの懸念も規制をかける理由の一つになっています。
上記は告知で加入できる限度額です。
例えば5000万円の保障が必要でライフネットで加入を考えた時、契約者の年齢が40歳だと限度額が3000万円になっていますね。
これだと複数社で加入しないといけなのかと思うかもしれませんが告知書扱いではなく診査扱いならば保障額は1億円までの設定が可能なので安心してくださいね。
職業による加入制限
年齢と同じように職業でも制限があります。
事務職で働くのと建築現場で働くのとでは危険の度合いが変わってきますよね。
職業の制限は各社で違いますが年齢とは違って限度額だけではなく加入そのものができない保険加入不可の場合があります。
加入が断られる可能性の高い職種
・レーサー
・スタントマン
・登山家
・プロの格闘家
・テストドライバー
・テストパイロット
・潜水士
・競輪や競艇選手
以上のように仕事中に危険を伴う職業は保険加入が難しくなっています。
加入はできても制限がかかる可能性がある職種
・消防士
・タクシー運転手
・トラック運転手
・高所ビル外壁清掃
・高圧電気作業者
・ガードマン
職業の制限は各社によって違います。
そのため同じ職種でもA保険会社は断られてもB保険会社なら加入できるという場合もあります。職業で謝絶された場合は他の保険会社を探してみましょう。
またかんぽ生命のように職業の制限をしていない保険会社もありますし、同じ保険でも商品によって職業制限がない場合もあります。
複数社扱う保険代理店に相談すれば、職業制限がかかるような職種でも加入できる保険会社、保険商品をピックアップしてくれます。保険相談を有効的に使ってくださいね。
収入による制限
年収の〇倍までしか加入できないと聞くことがありますが、私が保険代理店で働いていた時にはそのような制限はありませんでしたし、今も明確な数字として出している保険会社はないのではないでしょうか。
もしあるとしたら加入条件や引き受け基準に一定の年収がない場合は加入をお断りする場合がありますとか、年収の〇倍までしか加入ができませんという文言が書かれているはずです。
ではなぜ、はっきり明記されていないのに年収の〇倍までという基準がまことしやかにながれているのでしょうか。
必要保障額を計算するときにざっくりと年収の〇倍としていたものが間違って限度額と伝わったのかもしれませんね。
年収による限度額の制限はないとはいえ、保険料を払えなくなっては意味がないので支払って行ける保険料の額なのかということから制限がかかる可能性はありますね。
生命保険文化センターがまとめた生命保険に関する全国実態調査を見てみると平均の世帯年収は598万円で支出可能保険料は38.5万円です。大体年収の約6%が生命保険料として支払われています。
月収15万円だと保険料に使えるのは9000円ぐらいですね。
35歳男性で1億円の保障に入りたいといわれた場合、10年定期にしたとしてライフネットで試算したところ保険料は14060円になります。
この金額だと月収の10%近くになりますね。このように保険料の支払いが難しいのではと考えられる場合は代理店として契約を引き受けできかねるでしょう。
支払いができるのかといったことで保障額を抑えた提案になるため年収で制限がかかったと感じることがあるのかもしれません。
ただ実際には普通の会社員で1億円の保障額が必要な方はまずいないでしょうし、世帯主の普通死亡保険金の平均は1509万円です。
この保障額の保険料は先ほどの試算と同じ条件ならば2321円になりますので収入が問題になって加入できないということはまずないと考えてもいいのではないでしょうか。
保険の加入限度額があると思っていた保障に入れないかもしれない。と心配だった方もいらっしゃったかもしれませんね。
生命保険の限度額は若い時なら入れた保障額に年を取ってからは入れなくなるといったような年齢によっても変わるし、外で働く危険な仕事なのか危険とは程遠い事務職なのかといったように職業によっても変わってきます。
職業という点では相互扶助の考えから致し方ないことなのですが、年齢の制限については告知の場合のみですし、複数社加入することもできますので必要な保障額をまかなえないということはありませんので安心してくださいね。